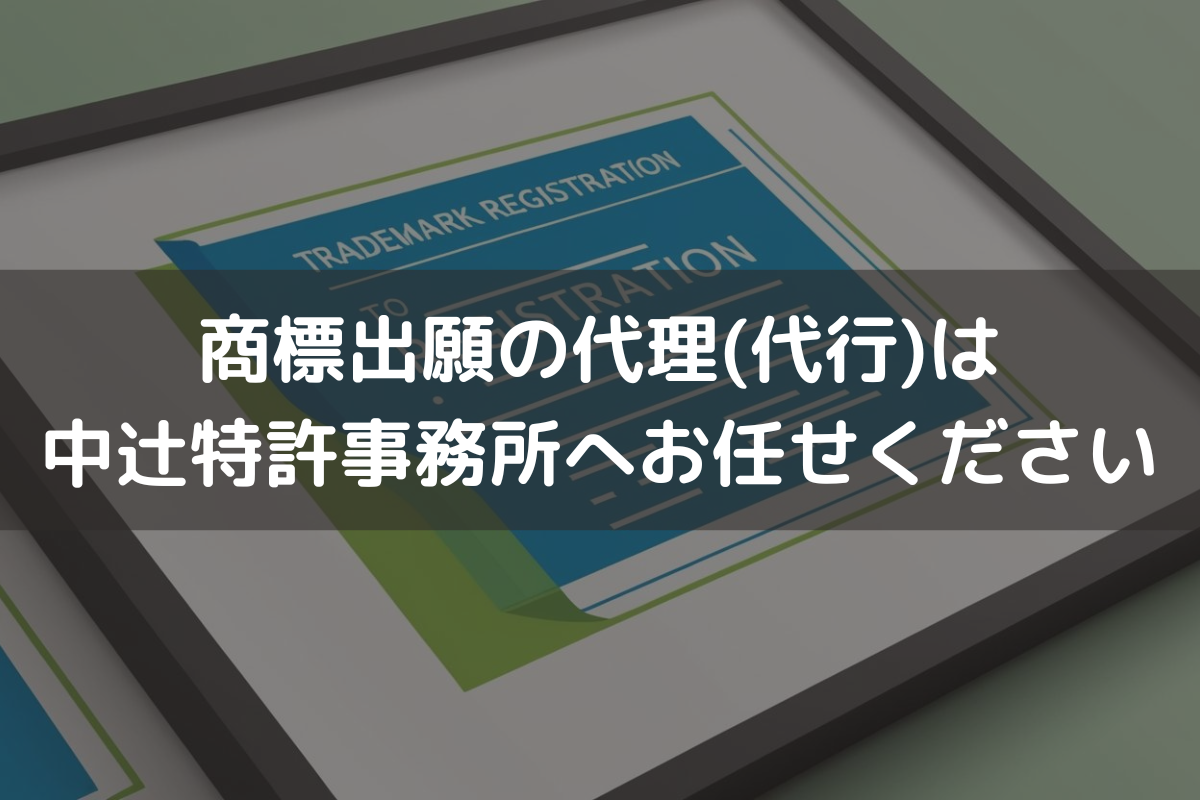
商標登録を受けるための出願は自社で行うこともできる一方で、専門家である弁理士に代理を依頼することも可能です。
では、商標出願の代理(代行)は誰に依頼すればよいのでしょうか?また、依頼先の選定にあたっては、どのような点を考慮すればよいのでしょうか?
今回は、商標出願の代理を依頼する代理人の選び方のポイントなどについて、弁理士がくわしく解説します。
商標登録とは
商標とは、商品や役務について使用される標章(名称やロゴマーク、色彩、立体的形状など)を指します。
せっかくブランディングをしようとしても、他社に同じまたは似た商標を使用されれば、差別化をはかることは困難です。そこで、大切な商標については商標登録を受けることが有力な選択肢となります。
商標登録とは、特許庁へ出願して商標の登録を受けることです。登録を受けた商標は自社が独占排他的に使用することが可能となり、他社による模倣を避ける効果が期待できます。また、他社に同じ(または似た)商標出願を先を越され、自社がその商標を使えなくなるリスクも回避できます。
商標出願の代理(代行)とは
商標出願の代理とは、特許庁への商標出願業務を代理人(弁理士、弁護士)に依頼することです。
商標出願は自社で行うこともできる一方で、代理人に依頼することもできます。商標出願を代理人に依頼すると、その後の特許庁との遣り取りも代理人経由で行うことになり、商標登録を受けるまでの間、代理人のサポートを受けることができます。代理人に商標出願を依頼することで商標登録を受けられる可能性を高めることが可能となるほか、無駄な出願を避けることも可能となります。
商標出願の「代理」ができる資格
商標登録の「代理」ができるのは弁理士と弁護士だけ
商標登録の「代理」とは、出願書類の作成のみならず、本人の代わりに特許庁への出願や特許庁からの問い合わせへの対応などをすることを指します。商標登録の「代理」を行えるのは、弁理士と弁護士に限定されています。これらの資格を有していないにも関わらず商標出願の代理をする行為は、違法です。
なお、弁護士が商標出願の代理を積極的に行っているケースは多くないため、事実上は弁理士一択となるでしょう。
商標出願の「代行」も弁理士と弁護士だけ
商標登録の「代行」とは、商標登録の出願書類の作成だけを代わりに行うことです。「代行」という表現は、知財業界で普及していませんが、次で紹介する「オンラインサービス型」を代行と呼ぶケースが多いようです。
代理とは異なり、専門家が本人の代わりに出願するわけではありません。商標登録の「代行」ができるのも、弁理士と弁護士に限られます。弁理士法75条、弁護士法3条2項の規定により、商標出願の書類作成だけであっても弁理士、弁護士以外の者は行えない旨が明記されているためです。
商標登録代行サービスの主な種類
商標出願の代理(代行)は、主に「オンラインサービス型」と「弁理士事務所型」に分類できます。ここでは、それぞれの概要を解説します。
オンラインサービス型
オンラインサービス型の商標登録代行とは、オンラインのみで商標出願手続きをサポートするサービスです。書類の作成だけがサポート範囲であるものが多く、ある程度定型的なサービスに絞ることで比較的安価な料金体系としているようです。なお、弁理士名を名貸しするのは非弁行為となるため、このオンラインサービス型であっても、弁理士が何らかの形で関与していると思われます。
内容については相談できずフォームに自身で必要情報を入力することで出願書類が出力されるもののほか、弁理士によるメール相談サービスが付帯しているものなどがあります。
弁理士事務所型
弁理士事務所型とは、弁理士が商標出願を手厚くサポートするサービスです。商標やその他の知財について弁理士に相談をしたり、将来を見据えた知財獲得のアドバイスを受けたりしたい場合には、こちらが向いているでしょう。
商標出願の代理(代行)を弁理士に依頼すべき主な理由
商標出願の代理(代行)は、弁理士へ依頼するのがおすすめです。ここでは、その主な理由を2つ解説します。
- 知財の専門家であるから
- 的確な事前調査が可能となるから
知財の専門家であるから
弁理士は、商標など知財の専門家です。そのため、出願する商標の選定や区分を決める段階からアドバイスを受けることが可能です。また、適切な商標や区分を選定して出願することで、登録を受けられる可能性を高めることにもつながります。さらに、商標の類否判断を行うためには経験が重要であるため、経験豊富な弁理士に依頼することが望まれます。
的確な事前調査が可能となるから
無駄のない的確な商標出願をするためには、事前調査が不可欠です。弁理士に依頼した場合は的確な事前調査が可能となり、登録の可能性を高めることが可能となるほか、無駄な出願を避けることも可能となります。
商標登録の代行先を決める前に知っておくべきこと
商標登録の代行先を選定する前に、いくつか知っておくべき事項があります。ここでは、あらかじめ理解しておくべき事項を3つ解説します。
- 商標登録は区分を選定して行うものである
- 商標は出願すれば必ず登録を受けられるものではない
- 無駄な商標を取得すれば維持費用がかかる
商標登録は区分を選定して行うものである
1つ目は、商標登録は「区分」を選定して行うものであることです。
商標登録を受けた場合は、その商標の独占的使用が可能になるとはいえ、これはすべての商品・サービスを覆うものではありません。商標登録は45に区分された商品・サービス(役務)の中から、保護を受けたい区分を選定して行うものです。
たとえば、第3類である「洗浄剤及び化粧品」についてだけ商標登録を受けた場合、他社が第43類である「飲食物の提供及び宿泊施設の提供」について同一または類似の商標を使用したとしても、商標法にもとづく差止請求や損害賠償請求などは原則としてできません。
この区分は複数選択することもできるため、広範な商品・サービスにおいてその商標を排他独占的に使用したいのであれば、複数の区分を選択して出願することとなります。必要な区分に漏れがあれば商標を適切に守れないおそれが生じるため、漏れのないよう注意が必要です。
とはいえ、やみくもに多くの区分を選択することは現実的ではありません。なぜなら、商標の出願手数料や登録料などは、選択した区分が多いほど高くなるためです。たとえば、商標登録料は「32,900円×区分数」であり、1区分についてだけ出願した場合には32,900円です。
一方で、ある商標を10区分に出願した場合の商標登録証は、329,000円(=32,900円×10区分)にも上ります。対価に糸目をつけないのであればすべての区分に出願することもできるとはいえ、これは現実的ではないでしょう。
そのため、実際に出願をするにあたっては区分の過不足が生じないよう慎重に検討する必要があります。
適切な検討には専門的な知識が不可欠であり、商標登録を受けるための出願代行は、この点についてもアドバイスを受けられる専門家に依頼するべきでしょう。
商標は出願すれば必ず登録を受けられるものではない
2つ目は、商標は、形式上書類を整えて申請したからといって必ずしも登録を受けられるものではないことです。
商標登録を受けるための出願代行や代理について、単に「手間のかかる書類を作ってもらうこと」と捉えている人もいるようです。しかし、確かにこのような側面もあるとはいえ、サポートの本質はこの点ではありません。
弁理士が商標出願の代行や代理をする場合には、その商標について登録を受けられる見込みをあらかじめ調査することが一般的です。そのうえで、仮にその商標では登録が受けられないとなれば、クライアント様のニーズに応じて他の方法を提案することとなります。
たとえば、「A」という商標について登録の見込みが低いのであれば「A’」という他の商標について出願を検討したり、他の区分での出願を検討したりすることなどです。また、他の商標や区分について出願するメリットがないとクライアント様が考えるのであれば、はじめから出願しないことで出願手数料などの負担を避けることも選択肢に入ります。
このように、商標登録の代行や代理を適切な専門家に依頼する場合には登録の可能性を高めることが可能となるほか、無駄な出願を避けることも可能となります。
無駄な商標を取得すれば維持費用がかかる
3つ目は、無駄な商標を取得すれば、維持費用がかかることです。
商標は出願時に費用が掛かることに加え、登録が認められた場合、最終的に登録を受けるためにも費用(商標登録料)の支払いが必要です。商標登録料は先ほど紹介したように1商標1区分あたり32,900円であり、登録を受ける商標の種類や区分数が多ければそれだけ費用が嵩みます。
そのため、多くの商標を出願することが必ずしも経営にとってプラスであるとは限りません。たとえば、「商標A」の登録を受けることで別の「商標A’」についても侵害される可能性が低くなるのであれば、あえて「商標A’」を別途出願するメリットは少ないでしょう。
商標登録の出願代行や代理を適切な専門家に依頼する場合、このような点からもアドバイスを受けることが可能となります。
商標出願の代理人を選ぶ際の主な視点
商標出願の代理人は、どのような視点で選定すればよいのでしょうか?ここでは、代理人を選定する際の主な視点を5つ解説します。
- 出願する商標の選定段階からアドバイスを受けられるか
- 事前調査をどの程度行ってくれるか
- 商標の出願実績が豊富であるか
- 長期的な事業パートナーとなってくれそうか
- 海外の商標制度についても相談できるか
出願する商標の選定段階からアドバイスを受けられるか
1つ目の視点は、「出願する商標の選定段階からアドバイスを受けられるか」です。
弁理士に依頼する場合、クライアント様の目的や将来の展望などを考慮し、出願すべき商標の選定や区分の検討段階からアドバイスを受けられることが多いでしょう。
一方で、安価なオンライン代行などではこのようなアドバイスはしてもらえないことが一般的です。結果的に登録が受けられなかったり無駄な登録をすることとなったりしたとしても、これは自己責任となります。
事前調査をどの程度行ってくれるか
2つ目の視点は、「事前調査をどの程度行ってくれるか」です。
商標登録を受けるための出願代行や代理を弁理士に依頼する場合、事前調査から担ってくれることが一般的です。この調査を踏まえ、出願すべきか否かのほか、出願すべき商標や区分の選定などのアドバイスがなされます。
一方で、安価なオンライン代行などでは事前調査はしてもらえないことが少なくありません。そのため、出願をした結果登録が受けられなかったとしても、特許庁への出願手数料や代行サービスに支払う報酬などは発生することとなります。
商標の出願実績が豊富であるか
3つ目の視点は、「商標の出願実績が豊富であるか」です。
自社に合った適切な商標出願をするためには、商標についての知識があることに加え、実際の出願サポート実績が豊富であることも必要です。そのため、特に重要な商標を出願しようとする局面では、商標出願の実績が豊富な弁理士に代理や代行を依頼するべきでしょう。
なお、弁理士であっても事務所にはそれぞれの「色」があり、商標出願にどれだけ力を入れているかは事務所によって異なります。
長期的な事業パートナーとなってくれそうか
4つ目の視点は、「長期的な事業パートナーとなってくれそうか」です。
弁理士への相談経験がない場合、何となく「敷居が高そう」であると感じている人もいるようです。しかし、本来弁理士は、商標など知財に関して困りごとが生じた際にまず相談できる「町医者」のような存在であるべきであると考えます。
自社における知財のパートナーともなるべき信頼できる弁理士を見つけることで、自社の知財レベルを格段に引き上げることが可能となるでしょう。
そのため、「かかりつけ」となる弁理士を見つけたいのであれば、まずは商標出願を入り口として信頼できる弁理士を探すことも一つの方法です。
海外の商標制度についても相談できるか
5つ目の視点は、「海外の商標制度についても相談できるか」です。
商標は「属地主義」が採られており、日本で商標登録を受けた商標が保護される範囲は日本国内のみです。日本だけで商標登録を受けた場合、その商標が中国国内で使用されたとしても、商標法を盾に有効な対抗措置をとることはできません。そのため、海外でも保護を受けたいのであれば、保護を受けたい国ごとに出願手続きをする必要があります。
グローバル化が進行している昨今では、海外と無縁ではビジネス展開が困難な企業も少なくないでしょう。そうであるにもかかわらず海外での知財保護に無頓着であれば、足をすくわれる事態となりかねません。
そのため、海外展開の可能性が少しでもあるのであれば、海外での商標登録についてもアドバイスを受けられる専門家を選定することをおすすめします。
商標出願の代理は中辻特許事務所へお任せください
商標出願の代理は、中辻特許事務所へお任せください。最後に、中辻特許事務所の主な特長を3つ紹介します。
- 弁理士の豊富な実務経験+最新AI商標調査でのサポートを行う
- 戦略的思考を得意としている
- 顧問契約も可能である
- 海外への出願のアドバイスやサポートも可能である
弁理士の豊富な実務経験+最新AI商標調査でのサポート
中辻特許事務所は、弁理士試験の試験委員も務められた経験豊富な福田弁理士をはじめとして、商標実務の能力に秀でた複数の弁理士によりサポートします。
一方、最新の生成AI技術を駆使したTM-ROBO(【公式】TM-RoBo、フルオプション)を複数アカウント導入して商標の検索、類否判断を併用しています。
戦略的思考を得意としている
中辻特許事務所の代表である中辻は、陸自幹部技術高級課程や陸自装備開発を経た異例の経歴を有しています。このような背景もあり、戦略的思考に特に強みを有しています。
ビジネスで戦う武器となる知財の威力を最大限に発揮したい場合には、当事務所がお役に立てます。
顧問契約も可能である
中辻特許事務所では、商標出願などの単発でのサポートのほか、顧問契約も可能です。商標や特許などの知財を活かしてビジネスを飛躍させたいとお考えの際は、まずは商標登録の代行・代理で当事務所の力量をお確かめください。
海外への出願のアドバイスやサポートも可能である
中辻特許事務所は海外における知財制度にも知見を有しており、海外への出願に関するアドバイスやサポートも可能です。海外展開をご検討の際にも、当事務所がお役に立てます。
まとめ
商標出願の代理(代行)の概要や代行先の選び方などを解説しました。
商標出願は自社で行う道もある一方で、代理や代行を依頼することも可能です。ただし、商標登録の代理や代行の具体的なサポート内容は、依頼先によって大きく異なる可能性があることに注意しなければなりません。
自社が商標について知見を有しており、単に手続きだけを代行してほしい場合には、安価なオンライン代行も選択肢に入るでしょう。一方で、出願する商標・区分の選定についてアドバイスを受けたい場合や事前調査を受けたい場合、海外展開も視野に入れている場合などには、弁理士へ直接相談することをおすすめします。
中辻特許事務所は知財を活かした企業の戦略構築を強みとしており、ビジネスを有利に進めるための商標出願について多くのサポート実績がございます。商標登録の代理・代行先をお探しの際は、中辻特許事務所までお気軽にご相談ください。

![20240829-00[fulldata]-06](https://nakatsuji-ip.com/wp-content/uploads/2022/09/20240829-00fulldata-06.png)